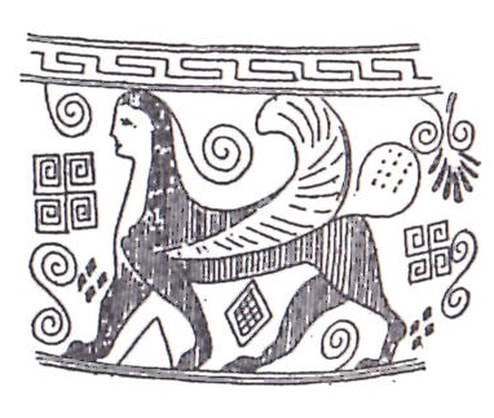占い入門その3 目次とリンク
占いのはじまりと歴史
占いのはじまりは古く、文字の発明と深く関わっています。
人ははじめ、大自然の働きに目に見えない力である神や霊を見い出し「万物に神霊がやどる」と考えました。
これら神霊からの言葉を知る手段としてできたのが占いです。
そして、目に見えない「観念」や「神の言葉」を目に見える形として残すために文字が生まれ、発展していきました。
分かりやすく言えばきざしを読み取る技術です。シンボルや象徴です。
シンボルについての説明はこちら
もっとも古い占いは卜占(ぼくせん)です。紀元前4~5000年の新石器時代の墳墓から、占いの道具が見つかっています。
亀の甲羅に納められた、色と大きさの違う複数の小石の出土は、当時の為政者が自ら占いを執り行っていたことを物語っています。
古代の人々が神霊と交信する手段として、問卜(もんぼく)という占いがあります。
問卜は、亀の甲羅や獣の肩甲骨を使った占いです。甲骨にいくつも穴をあけ、それらを焼いた後のひび割れの形によって、さまざまな吉凶を判断します。
卜という字は、このひび割れの形をあらわしています。また、甲骨を焼いたときの「ボク」という音から文字の読みがそのまま用いられ今にいたっています。占いという字も口の上に卜の字が見られますね。
日本では、弥生時代からあるこの問卜のことを太占(ふとまに)と呼び、今もわずかながら実践研究している方がいらっしゃいます。
人ははじめ、大自然の働きに目に見えない力である神や霊を見い出し「万物に神霊がやどる」と考えました。
これら神霊からの言葉を知る手段としてできたのが占いです。
そして、目に見えない「観念」や「神の言葉」を目に見える形として残すために文字が生まれ、発展していきました。
分かりやすく言えばきざしを読み取る技術です。シンボルや象徴です。
シンボルについての説明はこちら
もっとも古い占いは卜占(ぼくせん)です。紀元前4~5000年の新石器時代の墳墓から、占いの道具が見つかっています。
亀の甲羅に納められた、色と大きさの違う複数の小石の出土は、当時の為政者が自ら占いを執り行っていたことを物語っています。
古代の人々が神霊と交信する手段として、問卜(もんぼく)という占いがあります。
問卜は、亀の甲羅や獣の肩甲骨を使った占いです。甲骨にいくつも穴をあけ、それらを焼いた後のひび割れの形によって、さまざまな吉凶を判断します。
卜という字は、このひび割れの形をあらわしています。また、甲骨を焼いたときの「ボク」という音から文字の読みがそのまま用いられ今にいたっています。占いという字も口の上に卜の字が見られますね。
日本では、弥生時代からあるこの問卜のことを太占(ふとまに)と呼び、今もわずかながら実践研究している方がいらっしゃいます。
占いと政治
政治家には、それぞれ占い師が付いている。そのような話を今でも時おり耳にする人がいると思います。
実際にどうかと言えば、そういったことは今でもあります。
たとえば、選挙前に地域の神社で祝詞をあげてもらったり、占い師や風水師などに当選のための呪術的な依頼が来ることもあります。
選挙は水ものですので、当選するために「験を担ぐ」ことを大切に考えているというのも理由のひとつですが、もともと政治と占いは、互いに欠かせない関係にあります。
政治というのは政(まつりごと)を治(おさめる)と書きます。
まつりごととは神様の言葉を知ったり願い事をする儀式のことです。まつりの主催者はそこで最も偉い人がおさめますので、それで政治という言葉になります。
本来、人々から選ばれた代表的な立場に立つものは公(おおやけ)の人といって、その役目に自分自身の損得を持ち込まない人とされています。
私たちの国の公人で最も尊ばれている人は誰かといえば、それは天皇陛下です。陛下の公の務めは国や国民が安泰であるために祈りを捧げたり、他の国に出かけて日本の国はこのような平和な国ですよと体現されることです。まさに政を治める人そのままです。
古代では、国家の王が神霊の言葉を知るために占いをおこない、神託を指針にしていました。はじめは王自身が占っていましたが、王朝が安定するに従い、その役割はしだいに専門の官吏によっておこなわれるようになりました。神官の誕生です。神官が公人として認められている数少ない国のひとつが私達の日本です。
実際にどうかと言えば、そういったことは今でもあります。
たとえば、選挙前に地域の神社で祝詞をあげてもらったり、占い師や風水師などに当選のための呪術的な依頼が来ることもあります。
選挙は水ものですので、当選するために「験を担ぐ」ことを大切に考えているというのも理由のひとつですが、もともと政治と占いは、互いに欠かせない関係にあります。
政治というのは政(まつりごと)を治(おさめる)と書きます。
まつりごととは神様の言葉を知ったり願い事をする儀式のことです。まつりの主催者はそこで最も偉い人がおさめますので、それで政治という言葉になります。
本来、人々から選ばれた代表的な立場に立つものは公(おおやけ)の人といって、その役目に自分自身の損得を持ち込まない人とされています。
私たちの国の公人で最も尊ばれている人は誰かといえば、それは天皇陛下です。陛下の公の務めは国や国民が安泰であるために祈りを捧げたり、他の国に出かけて日本の国はこのような平和な国ですよと体現されることです。まさに政を治める人そのままです。
古代では、国家の王が神霊の言葉を知るために占いをおこない、神託を指針にしていました。はじめは王自身が占っていましたが、王朝が安定するに従い、その役割はしだいに専門の官吏によっておこなわれるようになりました。神官の誕生です。神官が公人として認められている数少ない国のひとつが私達の日本です。
易占い
さて、歴史をもっと広く昔にさかのぼって考えれば、紀元前15世紀ごろの中国では、筮竹(ぜいちく)と算木(さんぎ)を使った占いがおこなわれています。それは今から3700年くらい前のことです。
さらに、紀元前2世紀ごろ、周(しゅう)王朝の時代には、易(えき)の原典である易経(えききょう)が孔子(こうし)によってまとめられました。
この経典をテキストとして用いる占いを周易(しゅうえき)といいます。
日本には2世紀ごろ、すでに易の元になる考えが中国から伝わっていました。
5~6世紀になると、さらにさまざまな占いがもたらされ、8世紀には大宝律令という法律によって、占い専門の役所である陰陽寮(おんみょうりょう)が作られることが決められました。
そして、その陰陽寮では占いの他、星の観測や暦の作成が行われていました。
映画にもなった陰陽師、安倍晴明が有名ですね。
しかし、占いが庶民の間に広まったのはずいぶん遅く江戸時代になってからのことです。江戸時代の中期には、占いによって生計を立てる易者があらわれます。
なお、現在でも易占いでは昔からの方法をそのまま受け継ぎ、筮竹やコインがそのまま使われています。
さらに、紀元前2世紀ごろ、周(しゅう)王朝の時代には、易(えき)の原典である易経(えききょう)が孔子(こうし)によってまとめられました。
この経典をテキストとして用いる占いを周易(しゅうえき)といいます。
日本には2世紀ごろ、すでに易の元になる考えが中国から伝わっていました。
5~6世紀になると、さらにさまざまな占いがもたらされ、8世紀には大宝律令という法律によって、占い専門の役所である陰陽寮(おんみょうりょう)が作られることが決められました。
そして、その陰陽寮では占いの他、星の観測や暦の作成が行われていました。
映画にもなった陰陽師、安倍晴明が有名ですね。
しかし、占いが庶民の間に広まったのはずいぶん遅く江戸時代になってからのことです。江戸時代の中期には、占いによって生計を立てる易者があらわれます。
なお、現在でも易占いでは昔からの方法をそのまま受け継ぎ、筮竹やコインがそのまま使われています。